Non-Photorealistic Rendering
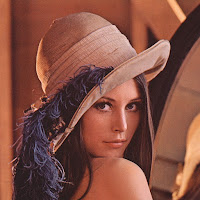
OpenCVにはNon-Photorealisticな画像に変換するための関数が用意されている。cv::stylization()やcv::pencilSketch()を用いることで、油絵や鉛筆画風の画像に入力画像を変換することができる。 入力画像 dst1 dst2 dst3 #include <opencv2/opencv.hpp> int main(int argc, char** argv) { cv::Mat image = cv::imread("../data/lena.bmp"); cv::Mat dst1, dst2; //鉛筆画風に変換 cv::pencilSketch(image, dst1, dst2); cv::imwrite("pencil1.jpg", dst1); cv::imwrite("pencil2.jpg", dst2); //油絵風 cv::stylization(image, dst3); cv::imwrite("style.jpg", dst3); return 0; }
